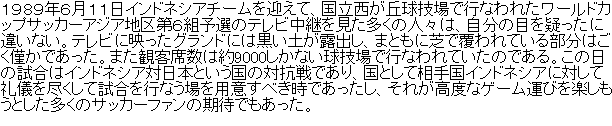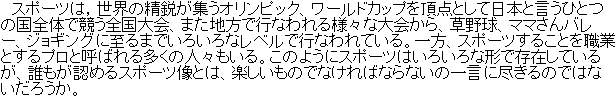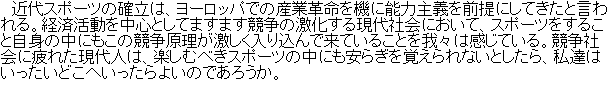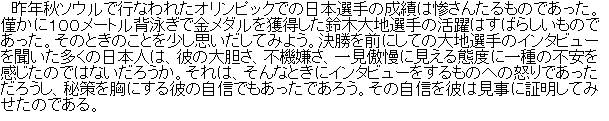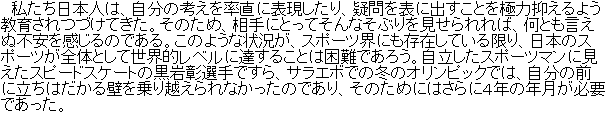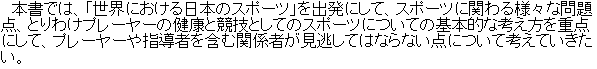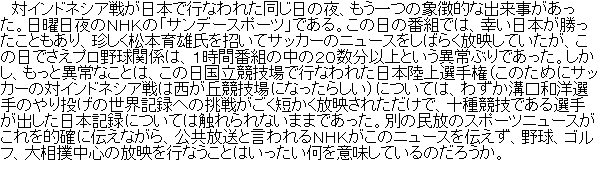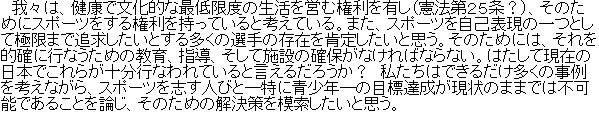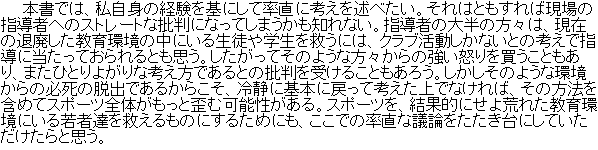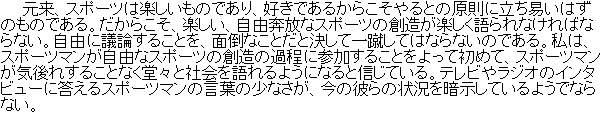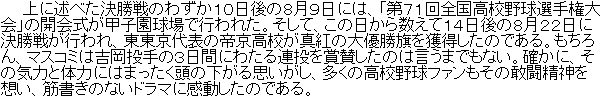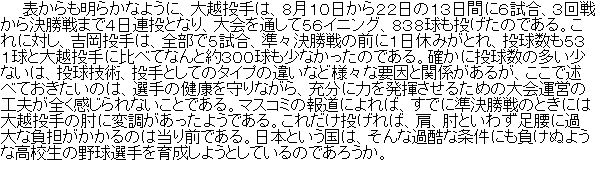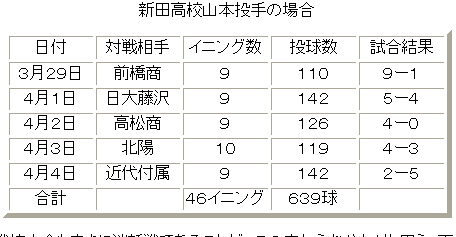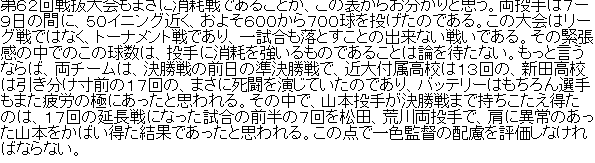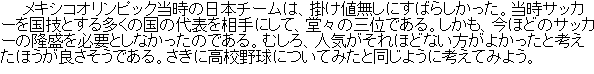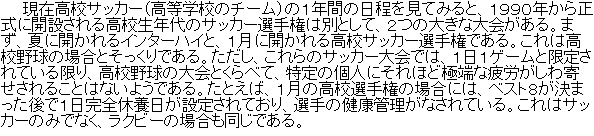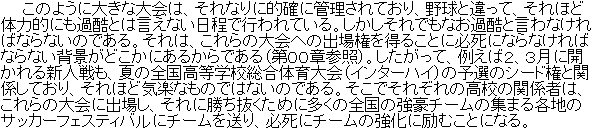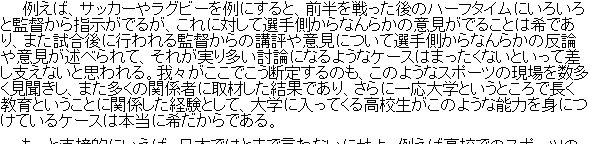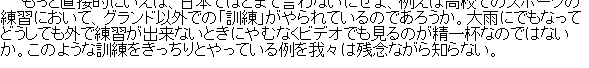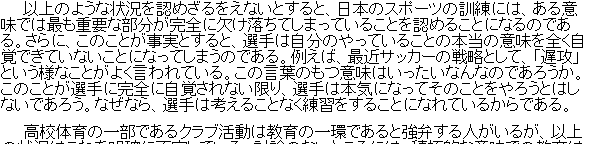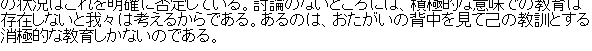|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メモ:
|
|
|
|
|
|
|
1990年春、私はそれまで思い詰めていた日本のスポーツ界の問題を友人や息子とまとめて本を出版しようと考え、断片的に書き始めた。しかし大阪大学に移動するという個人的な事情もあり、その試みは中断し、それ以降この本のことは忘れたわけではないが書き進めてはいない。書き進めなかったもうひとつの大きな事情は、プロサッカーとしてのJ−リーグの発足であった。川口チェアマンの発想は当時隆盛を誇っていたプロ野球に比較してはるかに斬新で、日本のスポーツ界に新風を吹き込むに十分であった。それ以降、日本のスポーツ界は徐々ではあるが変わりつつある。そして待望のW杯にも出場することになった。しかし相変わらず問題も多い。ここに、その時書きためたものを表に出しておくことは何かの役に立つことかもしれないと思い、フロッピーディスクから呼び出してここにおいておくことにした。暇があれば読んでいただければ幸いである。ただ、各セクションばらばらに書いたものであること、その間の調整も何もしてないこと、まだ書いてないセクションが山のようにあることもつけ加えさせていただきたい。残念ながら、いまこの本をどうにかしようという具体的なアイディアがあるわけではない。なお、以下のファイルの日付はファイルを最後に修正した日付になっていることをご承知おき願いたい(1998年6月4日)。
|
|
|
|
|

|
|
|
「日本のスポーツの限界」−仮題
|
|
|
|
|
「まえがき」(1990年6月24日)
|
|
|
|
|
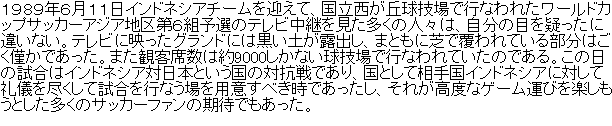
|
|
|

|
この日のゲームは、5ー0という圧倒的なスコアで日本の勝利に終り、日本のサッカーファンは、一時的にせよ溜飲を下げることになった。しかし。試合後に語られたインドネシアチームの監督の、「グランド状態が悪くて思いどうりのサッカーができなかった」との談話は、サッカー協会の関係者にとっては痛烈な批判となったであろう。というのも、その2週間前に相手国インドネシアで行なわれたインドネシア対日本戦は、絨毯を敷き詰めたような美しい芝生のグランドで、ほぼ10万に近い大観衆を収容できる競技場で行なわれていたからである。このようなスポーツをする場の悪さは、何もこの試合に限ったことではないことは言うまでもない。国立競技場の芝の悪さはもちろん、新しい地方の競技場ですら、その芝の管理は1年と続かないのが普通である。金余り国日本と言われながら、なぜこんなことがいつまでも続くのであろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
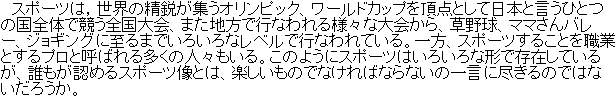
|
|
|
|
|
|

|
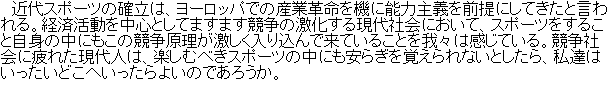
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
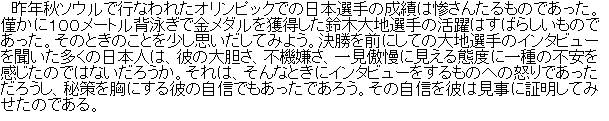
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
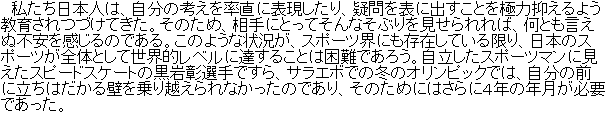
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私たちの自己表現のなさは、何もオリンピックを語らなくとも身の回りに幾らでもその例を見ることができる。後でも明らかになるように、高校野球の選手達もまた、自分達のけがを正しく監督に伝えられないようである。ましてや、高校進学のための内申書が重要な意味をもつ中学生には、なおさら同様のことが問題になるであろう。これらのことは、楽しく、健康ずくりに必要であるはずのスポーツ活動が、健康のためにも、教育のためにもなっていないのではないかと考えさせるものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
健康でバランスのとれた体づくりは、スポーツすることの最大の目標である。先にも述べたように、スポーツの世界の競争は、日本が国際化するとともにますます激しくなってきている。例えば、日本におけるサッカーの人気は、メキシコオリンピック直後のピークの後しばらく停滞したが、近年、少年サッカーを土台にして大きな広がりをみせ、再びオリンピックやワールドカップ出場への夢をかきたてるようになってきている。しかし、その壁は依然として厚い。そのような状況の中で、1977年少年サッカーの全国大会が読売ランドで始まったのである。この大会に出場する大多数の選手は、小学校6年生である。しかし、驚いたことに、1989年の今年、小学校5年生以下の選手による全国大会が神戸で始まったのである。このような年少者の属するチームが全国大会出場に血迷ったとき、小さく、言うべき言葉も持たぬ、発育ざかりの子供達の健康は十分守れるのだろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私の二人の息子が大好きなサッカーに没頭していた1982年から一年間、私たち一家は、私の仕事の関係もあってアメリカで生活した。その時期を選んだ理由のひとつは、それまでの数年間、サッカー漬けで少し疲れ気味の家族(妻、当時長男中学校1年生、次男小学校5年生、長女小学校2年生)を解放するには絶好のチャンスであったからである。行き先が、アメリカでも高いサッカー熱を持つカリフォルニアであったのはもちろん幸いであった。そこで子供達は、長女も含めてほんとにサッカーを楽しんだのである。サッカーをすること、スポーツをすることはなんと楽しく、また健康的であることかをあらためて家族一同実感した。2人の息子のチームは、サンフランシスコ近くの市とその地域で優勝したが、しかしカリフォルニア州大会や合衆国大会などは存在しなかったのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厳しい国際競争に耐えられる選手を育てるためには、小学校低学年からの専門化した厳しい肉体的訓練が必要だ、と日本のスポーツ指導者は本当に考えているのだろうか。信じられないことだが、事実はそうだと受け止めた方が良さそうである。本書の中で、私たちは、国際的なレベルで活躍できる選手の育成は、日本のスポーツのレベルアップのためには必要であるとの立場に立ちたいと思う。そして、それを考えることの中から、私たち素人が楽しむスポーツのレベルにも議論を拡大したい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
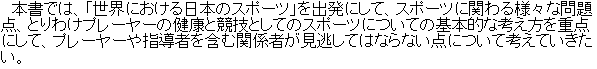
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
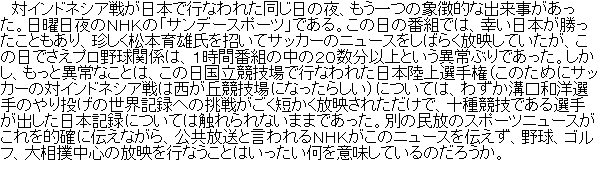
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
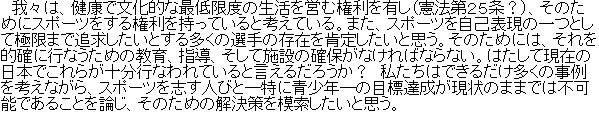
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
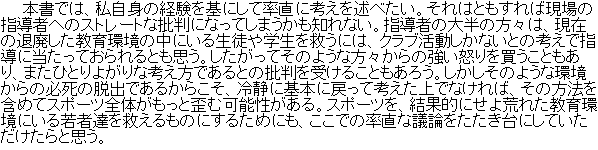
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
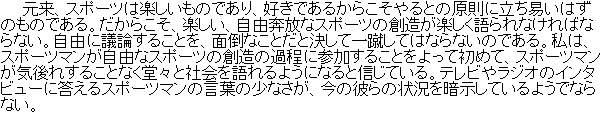
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
「 国内でのスポーツの実態」(1990年6月26日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この章では国内でのスポーツの実態、とりわけ小学校、中学校、高等学校で行われている団体競技がどの様な状況におかれているかについて述べてみたい。
|
|
|
|
|
|
|
|
「 過酷な高校生のスポーツ」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ほぼ義務教育化したといわれる高等学校での生活は、そこに学ぶ生徒にとっては、少年から大人へと飛躍するために重要である。肉体的にはなお成長期でありながら、限りなく大人の体に近付きつつある。精神的にも、例えば、将来の自らの職業について考え始める時期に当たり、そのための専門化志向を含めて、大学生という大人の世界へ向かう直前である。この過程には、大学受験地獄という残酷な付録が備え付けになっているにもかかわらず、なおエネルギッシュな時代である。いや、そうであるからこそ、スポーツに全精力を注ぎたいという願望が頭をもたげてくるのかも知れない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中学生でもそうだが、高校生を子供にもつ母親同士が話をするとき必ず話題になるのは、「おたくのお子さんは、何かスポーツをやってらっしゃいますか」である。「ええ、野球をやってます」となれば、「お金もかかって大変でしょうけど、スポーツでもやっててくれれば、悪いことを覚える暇もなくて安心ですよね」と言うような笑えぬ話になるのである。スポーツは、親にとってみれば、ひとつの安全弁に見えているようである。はたして、いろいろな意味で子供達にとって安全弁になり得ているのであろうか。そのひとつの例として、高校野球を考えてみたい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「高校野球」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毎年6月に入れば南の沖縄県から、続いて北の北海道から夏の「全国高等学校野球選手権大会」の地方予選が始まり、夏の始まりを教えてくれる。そして、決勝戦の終わる8月20日頃には、日本列島の夏の終わりを感じさせるのである。この間、ほとんどの国民が「一億総高校野球ファン」になるといわれるほど熱狂し、ラジオ、テレビ、新聞を含む全てのマスコミが総動員体制を敷いてこれを報道し、このため、この時期の電力消費量は、高いクーラーの使用率と相まって、夏休み期間であるにもかかわらず1年のピークを迎えることになる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
春の「選抜大会」もまたしかりであり、厳しい冬から待望の春の到来を教えてくれる。このように、高校野球は全国津津浦浦に何千万人といわれるファンをもち、私たちを楽しませてくれる。しかし、それは本当にまともなことなのであろうか?私たちは、ただそれを楽しんでいれば良いのだろうか?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989年夏の大会愛知県予選の場合
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
かって野球王国といわれ、現在も屈指の激戦区と言われる愛知県を例にとってみよう。1989年の予選参加校数は、172であった。予選は、県内の9つの球場で7月16日からスタートし、7月30日に熱田球場で決勝戦が行われ、東邦高校が優勝し、春夏連覇に向けて大きな期待がかけられることになった。しかし、この15日間に、優勝した東邦高校は、8試合を戦わなければならなかったのである。しかも、一度たりとも負けられないトーナメント形式であれば、選手にかかる緊張感は想像に難くない。一度でも負ければ、華やかな舞台からの転落を意味するのである。では、優勝した東邦高校と準優勝に甘んじた豊田西高校はどの様に戦ったのだろうか。東邦高校は、山田、西両投手で、豊田西高校はほぼ本田投手一人で投げきった。以下山田、本田両主力投手の投げたイニング数をその日付けと共にまとめてみた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日付 | 山田投手 | 本田投手 |
7月16日一回戦 | 2 | 0 |
7月17日一回戦 | 0 | 9 |
7月19日二回線 | 8 | 0 |
7月20日二回戦 | 0 | 6 |
7月22日三回戦 | 41/3 | 9 |
7月24日四回戦 | 0 | 9 |
7月25日四回戦 | 9 | 0 |
7月26日五回戦 | 4 | 7 |
7月28日準々決勝戦 | 3 | 9 |
7月29日準決勝戦 | 8
1/2 | 9 |
7月30日決勝戦 | 8 2/3 | 8 |
合計イニング数 | 47 2/3 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結局、山田投手は、15日間計8試合で472/3イニング、本田投手は、14日間計8試合で65イニング投げたことになる。特に最後の5日間に、山田投手は241/3イニング投げたのに対し、本田投手は33イニングも投げたのである。勝負は投手の疲労度だけではないのは勿論であるが、野外でスポーツをするのにはあまり適してはいない真夏の炎天下でのこのイニング数の差は、勝敗に大きく影響するのは当然である。勝負は結局、8−0で東邦高校の完勝であった。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第71回全国高校野球選手権大会の場合
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
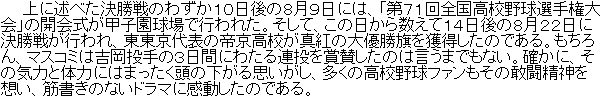
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
しかし、優勝した帝京高校の吉岡投手は、東東京予選が始まった7月13日から、甲子園球場での決勝戦の日までの41日間になんと11試合に投げていたのである。これはまさに消耗戦である。こんなことは、なにも優勝チームの投手だけに限ったことではない。敗れた準優勝チームの投手、あるいは、組合せによっては、準決勝戦あるいは準々決勝戦で敗れたチームの投手にも当てはまることであろう。しかし、このように多くの球数を投げるのは投手だけではなく、同じ球数だけ投手に投げ返している捕手も同じである。捕手の場合には、さらに、一球毎に立ったり、座ったりの動作が必要で、腰や膝に大きな負担になっていることは言うまでもない(第00章参照)。さらに、炎天下長時間熱砂の上にいる野手も、バッテリー程でないにしろ、その疲労は大変であろう。ここでは第71回の甲子園大会の決勝戦に出場した、帝京高校の吉岡投手と仙台育英高校の大越投手が、大会を通じてどれほどのイニング数と球数を投げたのかを以下まとめてみよう。
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仙台育英高校大越投手の場合
日付 | 対戦相手 | イニング数 | 投球数 | 試合結果 |
8月10日 | 鹿児島商工 | 9 | 162 | 7ー4 |
8月16日 | 京都西 | 9 | 112 | 4ー0 |
8月19日 | 弘前工 | 9 | 138 | 2ー1 |
8月20日 | 上宮 | 9 | 123 | 10ー2 |
8月21日 | 尽誠学園 | 10 | 167 | 3ー2 |
8月22日 | 帝京 | 10 | 136 | 0ー2 |
合計 | | 56イニング | 838球 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
帝京高校吉岡投手の場合
日付 | 対戦相手 | イニング数 | 投球数 | 試合結果 |
8月14日 | 米子東 | 9 | 118 | 3ー0 |
8月18日 | 桜ヶ丘 | 7 | 92 | 10ー1 |
8月20日 | 三重海星 | 6 | 72 | 11ー0 |
8月21日 | 秋田経法大付 | 9 | 112 | 4ー0 |
8月22日 | 仙台育英 | 10 | 126 | 2ー0 |
合計 | | 41イニング | 531球 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
帝京吉岡投手は一回戦不戦勝のため、大会6日目の14日に米子東高校を118球で完封した後、3日間の休養をし、18日に桜ケ丘高校に93球で完勝して20日からの準々決勝に備えることになった。一方、仙台育英高校の大越投手は、大会2日目の10日に162球投げて鹿児島商工を封じ、5日間の休養の後の16日の対京都西高戦で、112球であわやノーヒットノーランかの快投を演じた。大越投手は、吉岡投手と違い、準々決勝戦の前日の19日に弘前工高を相手に138球の苦しい投球をしていたのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
準々決勝戦からの仙台育英の試合は、まさに死闘といってよいであろう。その中で大越投手は、20日には優勝候補の筆頭で強打の元木選手を擁する上宮高戦では、123球投げて力でねじ伏せ、準決勝戦の対尽誠学園戦では、延長10回、167球のふんばりをみせたのである。よく考えてみれば、決勝戦前までの3日間の連投だけですでに428球投げていたのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一方、吉岡投手は、準々決勝戦、準決勝戦と相手チームの主力投手の疲労と思われる故障のため比較的楽に試合を進め、決勝戦直前では、2日間連投の194球で切り抜けられたのは、足首捻挫という故障上がりであった彼には確かに好運であったと思われる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上のようなデータをみると、決勝戦を前にして状況は明らかに仙台育英に不利であった。決勝戦では、押し気味に試合を進める仙台育英に対し、吉岡投手は鋭い切れ味のストレートと変化球で余裕をもってこれに対処し、ピンチに必死になって力投する大越投手と対照的であった。結果は、最後に集中力が切れ、力尽きた大越投手が適時打を浴び、帝京の優勝となったのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
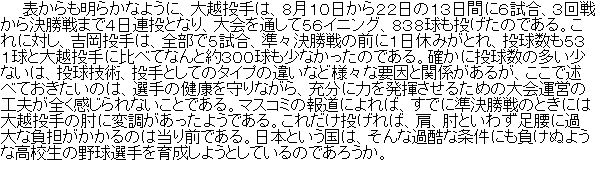
|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
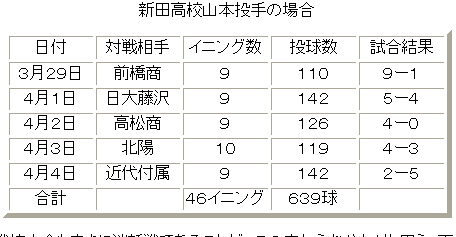
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
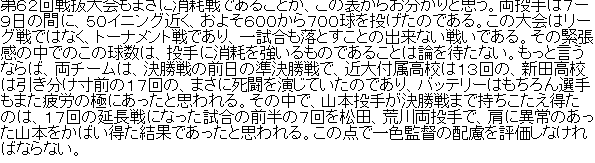
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ここまで述べてきた全国高校野球大会の過酷さは、なにもこの年に限ったことでないことは言うまでもない。また、全国大会レベルのことだけではなく、最初に述べたごとく地方大会でも全く同じであり、場合によっては、甲子園大会出場の夢がかかっているだけより過酷である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
このように考えると、甲子園とははたしてなんであろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「高校サッカー」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
忘れもしないのは、メキシコオリンピックで日本が銅メダルを獲得したことである。しかし、それ以後の日本代表の弱体ぶりは目を被いたくなるような状況である。その大会以来のサッカーの人気が、日本リーグの開設などもあって、小学生から高校生までは野球の人気を凌ぐほどであるにもかかわらずである。なぜこんなことになるのであろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
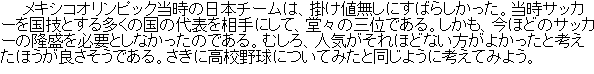
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
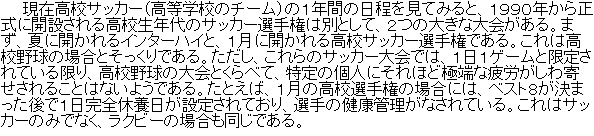
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
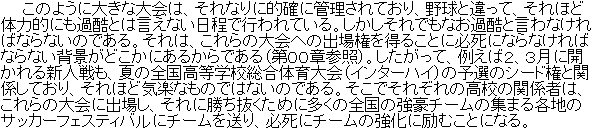
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
インターハイの予選が終わる6月には、秋に行われる国民体育大会(国体)に向けての県レベルでの選考が始まるところが多い。一般的には、これが8月末まで続き、最終決着までチームの強化に向けて、近くの県への何度かの遠征を行って練習試合を繰り返す。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国体が終わる10月には、翌年の1月に行われる全国高校サッカー選手権の予選が始まり、12月には決着がつく。こうしてみると、優れた運動能力とセンスを持つ選手を集めた有力校にとってはおよそ2ヶ月にひとつの大会があることになる。これに加えて、それぞれの地域での練習試合を考慮に入れると、放課後から夜までの厳しい練習のうえ、ほとんどの日曜祝日が試合に明け暮れる生活になっていることはよく知られている。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高校生時代とは少年から大人への大切な転換点である。従っていろいろなことに興味をもてる、またもってほしい年代である高校生にとって、サッカー漬けの、サッカー以外考えられない生活を送ることは何を意味するのだろうか。この時期、社会生活に必要な様々なことを授業を通して学び、様々な個性をもつ友達と話し合うなどの余裕をもった生活が必要であるにもかかわらずである。私からみれば全く残念な生活といわざるを得ないのである(第0章参照)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この点は野球選手の場合も全く同じであり、陸上、ラクビー、ハンドボール、テニス、バスケットボールなどのほとんどのクラブ活動についても当てはまると想像される。私は、このような高校時代の生活様式が、根性論に支配される面白味のない、型にはまったスポーツを生み出す大きな要因のひとつであると考えている(第00章参照)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990年6月、過去8度の甲子園大会への出場を果たした三重県立明野高等学校野球部監督の富士井氏が、選手父母からの金品の授受の疑惑を三重県県警から追及され、自殺した。彼のそれまでの豪放な野球のことを考えると全く残念である。ことの真相は不明だが、この件とは別に全国どこでも、感謝の気持ちのレベルを超える金品の供与が父母の側から監督やコーチに贈られているとの噂が絶えない。これは過熱する高校野球ブームが招いた社会問題であり、単に選手と指導者、父母だけの問題ではなく、現在の高校スポーツのもつ構造的な問題を内抱していると考えるべきであろう。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「全国大会もある小、中学生のスポーツ」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和00年まで禁止されていた小、中学生のスポーツの全国大会が、国レベルのスポーツ水準の向上を目的にして昭和00年に解禁された。たとえば全国少年サッカー大会は、1977年に川崎市の読売ランドで始まった。それ以降この大会は、全国の小学生5、6年生ぐらいのサッカー少年や指導者の憧れの的になり、都道府県レベルでの予選は、高校野球やサッカーの予選に匹敵するほどの過熱ぶりである。ある程度のレベルのチームにいる選手であれば、その練習日程や試合日程の過密ぶり、遠征の回数などは、一般の人には到底信じられないほどである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たとえば愛知県を例にとれば、春5月から6月には全国大会の県予選が行われ、夏7月末から8月始めにかけて約1週間の日程で、炎天下の読売ランドで大会が開かれる。これが終われば、秋の大会に向けての強化が始まり、合宿や県外への遠征が何度か行われる。さらに秋から冬休みにかけていくつかの大会が開かれ、学年末にかけて県レベルの新人戦がおこなわれて1年の日程を終わる。試合は夏休みや冬休み中を除いてすべて日曜祝日に行われることから、熱心な家庭の父母は、ほとんどの休日に応援かボランティアとして試合に参加することになる。繰り返し言うが、これは高校生の日程とほとんど変わらないのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
もっと驚いたことに、ここ数年の間に全国各地で5年生、4年生そして3年生大会が行われるようになったのである。体の成長が始まったばかりの子供達をいったいどうしょうと言うのだろうか。私には常識的にみて考えられないことである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
このような強化が行われる少年サッカーは、世界的にみても確かに強い。1989年8月に東京で行われた世界大会でも、日本代表は前年に引続き圧勝であった。日本以外の国が国代表という点にそれほどこだわっていないという事情があるにせよ、技術的、体力的にみて段違いの差があるのは事実である。これほどの高いレベルは、確かに小学生を対象とするとは思えない程の練習メニュー、試合数に支えられていることは確かであろう。しかし、このような小学生が中学生、高校生、大学生、そして社会人になるにしたがって、世界のレベルとは大きくかけ離れた存在になってしまうのはどうしてだろうか。このあたりの事情は、小学生や中学生の学力が国際的にみて極めて高いレベルにいながら、大学生以降にレベルダウンしてしまう事情と全く同じであることに注意したい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
野球はどうか。リトルリーグに所属する選手は、基本的には上に述べたサッカーの場合と同じである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「スポーツと教育」(1990年6月19日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「受験生とスポーツ選手」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「受験生とスポーツ選手」という見出しは、奇妙に思えるかも知れない。しかし私には両方が全く同じに思えるのである。つまり、どちらの人間もどちらか片方しかやってないという意味である。もっと言えば、「受験生よ、威張るのではない。君達はスポーツさえ楽しめないのではないか」と。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大学受験を控えた高校生は、大好きなスポーツの部活動もやめ、受験勉強に必死になり、大学に入ったときにはおよそ2、3年も勉強を休まなければならないほど憔悴しきっているのである。これは極論ではなく、例えば在る国立大学に入学してきた学生を観察すれば簡単に分かることであって、一般に通用する話なのである。現状を言えば、とことんスポーツをやってみたいと思えば、受験勉強する時間をほとんど切捨て、高校3年生の最後の大会まで頑張らなければならない。受験勉強していない選手にとっては、多くの大会でよい成績をあげ、その戦績評価によって大学のスポーツ推薦の枠を突破しなければ、大学に入る道も閉ざされるからである。運よく大学に入ってからも、一般入学生のように、しばらく休養している余裕は全くなく、がむしゃらにやらなくてはレギュラーの道は遠い。私からみれば、スポーツをとことんやろうとする者の方がはるかに過酷な生活を余儀なくされていると思われる。このことは、高校生のみならず、中学生にもそのまま当てはまる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本には「文武両道」という言葉がある。これは、勉強もスポーツもやれる人間でなければならない、というような簡単な言葉ではないであろう。むしろ、この2つは相互に補完するものであり、どちらの道に進もうとするものにとっても二つを切り離すことは出来ないとの意味である。しかし、この言葉を生み出したこの国ほど、「文」と「武」を切り離す生活を学生諸君に迫っている国も珍しい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第00章に引用した朝日新聞の記事にもあるように、例えば高校野球の場合、一日の練習時間は5時間を越えるという。しかもただ易しい練習をしているのではなく、厳しいスパルタ式練習が大半である。さらに、休日は殆ど練習試合や公式試合に当てられるとすると、家にかえってすることはただ体を安め、怪我を早く直すことしかない。勉強する時間など殆どないのである。いや、勉強する気力など生まれようがないのである。その結果よっぽどでなければ、偏差値の高い学校には入れないことになる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通の学生は、これと全く逆のことをすることになる。授業の後には塾に通い、夜にはテレビもそこそこに勉強に精を出し、夏休み冬休みには予備校の特別学級に出席して受験対策に没頭する。よくよく考えてみれば、上に述べた学生は、この国の教育制度と文化の両方の遺産として、分離させられた生活をしている2種類のグループに属しているのである。多くを語る必要はあるまい。ただ、どちらに重点を置いたかの違いである。いずれにせよ、自分の時間をもち、自分のこと、友達のことそして社会のことを考える時間をもつことはできないのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一方、このように学生を2つに解離させ、一人の人間をもずたずたに切り割こうとする現在の社会の在り様を直感的に察知し、またこれに反抗しょうとする若者達が、いわゆる落ちこぼれとして必然的に生まれてくるのである。1990年の文部省の発表によれば、00万人の高校退学者があったという。このような退学者が多くなったということは、教育が荒廃し、受験勉強に精を出す学生の心も、スポーツに精を出す学生の心も荒廃しつつあると考えるのが当り前の考え方であろう。教育が荒廃しつつあるときに、学生スポーツが、そしてその延長線上にある社会全体のスポーツが発展しつつあるなんてことは考えられないことであろう。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「文武両道」を建前とする高校や大学は数知れない。しかし、ひとつの学校の中に勉学に精を出す学生とスポーツに精を出す学生が共存することが大事なのではない。間違ってもらって困ることは、このような「文武両道」で学校の評判が良くなることではなく、一人の人間の中に「文武両道」を備えた学生を育てて学校の評判が良くなることなのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上でも述べたごとく、市や県レベルである程度の戦績を残せる中学校や高校でスポーツをする生徒にとっては、勉強に当てられる時間はきわめて少ない。従って、成績も芳しくなく、入れる大学も限られることになる。そしてそれが社会に出るまで続く。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「スポーツと考えること」(1990年6月19日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「スポーツは文化である」。これは、日本オリンピック協会総務主事岡野俊一朗氏がよく口にする言葉である。これに私も賛成である。広く言えば、文化とは一人一人の人間の生きている証である。「文化」は文化であることを意識して造り上げていくものではなく、各人が最善の努力をして生きた結果として「文化」が造り上げられていくのである。この意味で、スポーツ活動そのものが「文化」であろう。それだけに、スポーツ活動はその土地、その国の「文化」の影響を色濃く受けている。すなわち、その国の人々の生き方、考え方がその国のスポーツのありかたに大きな影響を与えることになる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岡野俊一朗氏は、1989年0月00日夜00時00分からのNHKラジオの放送で、「我が国では、スポーツは首から下でやるものだと考えている人が余りにも多すぎる。今や頭を使ってスポーツをやらなければ、よい成績を上げることは難しい。これをやるためには、指導者自身がこのような考え方を改めない限り進歩は期待できない」との主旨のことを述べている。私も全く同感である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
では、なぜ我が国では頭で考えてスポーツをする習慣がないのであろうか。第00章で述べたごとく、日本におけるスポーツ、特に外来スポーツは、明治時代の富国強兵策の一環としての地位を与えられてきた。そのため古来からの日本人の文化的遺産に加えて、軍隊式の上意下達の人間関係を基本とする考え方が、スポーツを支配することになったと考えてよいであろう。このような事情は、何もスポーツの分野に限ったことではないのは勿論である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戦国武将の支配する中世における人間関係は、日本と外国との間に基本的に大きな差があったとは思えない。しかし、現代を規定する結果になった近代ヨーロッパにおいては、自由と平等を旗印とした民衆による革命によって基本的人権が確立され、それまでの人間関係の再構築に成功したのである。そしてスポーツをする権利さえ獲得することになったのである。しかし、我が国においてはこのような経過をとらず、一種の革命と言われた明治維新も一部の武士によって行われたもので、大衆が自ら自覚することとならなかった。そして、第二次世界大戦の敗北によって初めて基本的人権が大衆に与えられたのである。当然のことながら、それまではスポーツを楽しむ権利も与えられず、軍事教練の一環でしかなかったのである。この敗北にしても、民衆の峰起によってもたらされたものではなく、ヨーロッパにおける民衆の地下運動を伴った勝利とは全く趣を異にするのである。従って、スポーツにおける大半の権利、すなわち練習方法、試合方法、試合の日程そして施設などは、政治の場合と同じく、いまだに指導者側に握られているといっても過言ではない。誤解を恐れずに言えば、我々はいまだにスポーツをやらせてもらう立場にいるのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに、上意下達の意識がスポーツにおいて顕在化する理由は、ときに体力の限界に挑むような練習が必然化することがあり、それを力でもってやらせることが指導者の指導者としての力量であると、スポーツをする側と指導する側の双方に錯覚し易い点があるように思う。このようなことが日常化する結果として、スポーツの世界における縦社会の形成がより強化され、安定したものとして定着しているのである。もちろん、前にも述べたように、このような縦社会に依存する気持ちは、日本人の心の隅ずみにまで入り込んでいる。別の言葉で言えば、日本の社会は「看板社会」であり、自分より大きな看板―知識量としてもよいし、地位としてもよい―をもった人には、盲目的に従属し、逆に自分より小さな看板をもった人には高圧的に振舞うのである。そして、これに違反したときには、当然のように社会としてこれを摘発する。出る杭は打たれるのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最近は変わってきた、と言う人もいる。しかし、若者を中心とするブランド志向の流行は、上に述べたような意識がより強化されつつあることを証明している。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
このような状況の中で、スポーツをする人、とりわけスポーツ選手は考えながら練習や試合にのぞむことが出来るのだろうか。もし、この状況に「技術は体で覚えろ」という、よく指導者が口にする言葉を付け加えたらどうか。読者は、「とても考えてはいられない」、「いったい何か考えなければならないことがあるのだろうか」と頭を抱える人が多いと想像する。そして、「ただ練習あるのみ」とか、「ふだんの練習の力を出すだけ」との結論が自動的に出てきてしまうであろう。書いている私でもはたと困るのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
でも、ちょっとスポーツのあり方を眺めてみれば、この世界も大きく変わってきたことにすぐ気が付く。たとえば、スポーツ選手の練習の中に必ずあった「うさぎ跳び」はなぜなくなってしまったのだろうか。かっては、野球選手は肩などを冷やすので泳いではならないとされていたにもかかわらず、今は「アイシング」などと称して投球練習後や試合後のピッチャーの肩や肘を氷で冷やすのは何故なんだろう。棒高飛びや高飛びの方法の変化も著しい。各種スポーツの戦略もここ10年、20年の間に様変わりしてしまっている。このような変化は数限りなくある。残念ながら、これらのほとんどは日本人でない誰かが考えたのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポーツがかってのただの遊びであった時代から、現在は多くの人たちがその人のある時期の大部分の時間を費やす対象へと変わってきている。また、ことの善し悪しは別にして、スポーツを支える環境は大きく変化し、経済を大きく動かす可能性すらあるものに変わりつつある。このように考えると、もはやたかが遊びではすまなくなってきている。しかも、スポーツに自分の人生を賭けようとする多くの若者がいる以上、スポーツをすることの中から彼らが何かを学べるようにしなければならないのである。現在、スポーツ選手が信頼に足る存在と見なされているとは思わない。好きであるはずのスポーツをどうすれば苦しくとも楽しめるものにするかを考え始めなければ、彼らはいつまでも世間一般からスポーツ馬鹿といわれ、ほんとの意味で社会的に信用される存在になれないのである。 昭和35年の新安保条約改定のとき、日本中が反安保運動で騒然とした。その時、当時の岸首相は「それでも後楽園球場は満員である」と豪語し、「声なき声」に耳を傾けると述べたのである。しかしこの時でもまだ、東京大学の野球部をはじめとして多くの大学の体育会は、積極的にこの問題を考えようとした(文献)。しかし、それからおよそ10年後の大学紛争時には、多くの大学の体育会はその暴力的体質をあらわにすることになった。不思議なことに、このような変化と日本のスポーツ界の国際的なレベルからの転落とは時期を同じくしたのである(第00章参照)。以上のような私の言い分は、一方的であることは明かである。しかし、この時期以来、学校でのスポーツの指導者や選手による暴力事件が多発し、マスコミを騒がし続けていることは事実である。いまさらこのことについて資料を取り上げる必要はあるまい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私は、生物学の研究と教育を職業として生きている。この中で一番大切なことは、自分の仕事を面白いものとして感じられているかどうかである。もしほんとに面白いと感じていれば、自分の目標をその都度設定し、それに向かって必要な討論をまわりの研究者と行い、それを遂行するであろう。しかしそれを面白いと感じていないならば、何も考えずに言われたこと、与えられたこと、また流行のことをただやっているだけのことになるであろう。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校のスポーツクラブに属する生徒や学生は、就職に大変有利であるといわれる。これはスポーツ選手が、体力があり、集団行動になれており、上司の命令に従順であることが評価された結果であると私は判断している。日本の社会が、上意下達の意志伝達機構をもった年功序列の縦社会であり、これを支える企業や役所がスポーツ選手を好んで採用するのは当り前である。残念ながら日本の社会は、基本に戻って物事を考えようとする気風に欠けると言われて久しい。このことは、いっけん難しそうに見える生物学を仕事にする私や、たかがスポーツなどといわれながらスポーツをする若者をはぐくんでいる土壌は同一であり、共に創造的といわれるように物事を考えない存在に過ぎないのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この章の前半で私は、スポーツ選手を、彼らを取り囲む社会の構造から考えて、彼らを「体育会的体質」をもち、何も考ええない存在として規定した。しかし、この同じ社会に生きる私のような存在もまた、「専門馬鹿的体質」をもち、基本に戻って物事を考えられない、同じ欠陥を持った人間であるはずである。ただ違うのは、一方が明らかに「学問」といわれる「文化」に属し、他方が「遊び」と思われているだけである。もし、前述したようにどちらも「文化」であるとすれば、もはや何の区別もできない。ここではじめて私は、自分の経験に基づいて大好きなスポーツの世界を語る資格があると判断したのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私自身が、自分の仕事を面白いものと自覚しているかどうかは、ある程度は、自分の日常生活をよく観察すれば分かることである。そして、正直に言えば、ほんとに生き生きと働けるときはまれにしかない。ここから抜け出したいと思えば、しょせんは「考える」ことを前提にして、うろうろと何かを捜しまわらなければならない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポーツをするものにとっても事情は同じであろう。もしスポーツ選手が、試合で走り回っているように、いかにもはつらつと生きられていれば、流行の言葉である「燃え尽き症候群」なる言葉は生まれてこないであろう。もし、この言葉のもつ意味を選手と指導者の双方が真剣に考えなければ、スポーツ選手はいつまでも体育会的意識から抜けきれないであろう。同時に、高校を出た時点ですでに燃え尽きて、本来の目的であったはずの、大人の体でスポーツをする意欲を消耗させるという最悪の事態を温存するのである。ただグランドで大声を出しているだけと言うのは、いかにも残念である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「スポーツと健康」(1990年6月19日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教科書的にいうスポーツの意義は、意識するしないにかかわらず、健康な肉体を作り上げ、それをもとにして強靭な精神を養うことにあるであろう。しかし、現代的な意味を考えてみると、ストレスを解消し、リラックスすることにもっと重点があるように思える。 ここで最も重要なことは、成人してからの長い年月を健康に過ごすためにスポーツをすることである。子供達(高校生もふくむ)が、たとえスポーツが好きだからやるにせよ、この点を忘れさせないような指導が急務である。もし、このことが守られているなら、私たちはこのような本を書くことも考えなかったであろう。また、この点がよく理解できている指導者が大勢を占めているならば、日本のスポーツの限界を危惧することもなかったのである。この点がきちんと守られていないことを、以下いくつかの例で示すことにする。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第71回全国高校野球選手権大会の場合(1989年)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第00章で述べたごとく、この大会での優勝戦に登場した2人の投手の投げたイニング数、投球数は炎天下でのプレーであることを忘れても、私たちには気違い沙汰のように思えた。確かにテレビの画面でみる2人の投球は、気迫に満みちており、心配するに当たらないように見えたかも知れない。しかし、この大会中800球以上投げていた仙台育英高校の大越投手の投球は、よくみれば、それまでの投球とは異なり、スピードも球の切れももうひとつで、確かに気力で投げていた感があった。後からの報道によれば、準決勝戦頃から肘の異常を感じていたようである。これに反して、帝京高校の吉岡投手はテレビでの画面でみる限り、絶好調のように見えた。これは第00章で述べたごとく、比較的少ない投球イニング数と投球数と、足の故障のために東東京予選での投球数の少なさが幸いしたように思えた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
問題はこれだけではない。たとえば秋田経法大付属高校1年生の中川投手の場合である。8月14日に9イニング、124球投げ、18日に130球投げて準々決勝戦に進んだ中川選手はもはや限界であった。翌20日の準々決勝戦の相手は福岡大大濠高校、痛めた肩をかばってスローボールを多投し(報知高校野球,1989,No.5)、相手の目先をかわす頭脳的な投球で9回112球投げ、1−0でこれを破るのが限界であった。21日の準決勝戦では帝京高校に6回でノックアウトされ、1年生の夏を終わった。しかし、わずか1週間の間にほぼ5試合を投げた1年生投手中川選手の活躍はマスコミで大きく報道され、賞賛されたが、この大会での無理が後に大きな禍根を残すことになった(00ページ参照)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
もっと例をあげよう。三重県勢として21年ぶりのベスト8まで進出した三重海星であったが、問題を抱えていた。8月14日9イニング、150球、4日後の18日9イニング、114球投げて準々決勝戦まで進出する原動力になった森投手も、2日後の20日の対帝京戦では疲労のため投げられず、湯浅監督は喜田投手を先発させたが、力不足で完敗した。試合後の海星の湯浅監督の「つくづく投手は2人必要と痛感した」との談話は印象的であった。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、尽誠学園の宮地投手も、8月11日9イニング、118球、16日9イニング、123球で勝ち進んだ後、19日の対神戸弘陵高戦ではすでに発熱していたという(報知高校野球,1989,No.5)。極度の疲労による発熱と思われる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第62回選抜高校野球大会の場合
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この大会の初日は、まさに印象的であった。開会式直後の第一試合には、前年の夏の甲子園大会で1週間の間に5試合投げた秋田経法大付属高校の中川投手は、2年生の春再び甲子園に登場した。昨年同様うまみのある投球をみせたが、しかし昨年のようなキレのある球がみられず、9回に鹿児島実業高校の猛反撃を浴びて逆転負けを喫した。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この試合には私たちの注意を引く二つのことが隠されていた。前年の夏の大会での投げすぎで肩をこわした中川投手は、今年の1月まで投球練習が出来なかったという(NHKスポーツニュース)。投げ込み不足は明かであった。それだけではない。選抜大会出場の重要な選考会である秋の地域対抗戦には、肩痛のため投げられなかった中川投手に代わって、斉藤投手がふんばり、選抜大会への出場権を獲得したのである。しかし全く不幸なことに、斉藤投手はそのために肘を痛め、本大会では全く投げられる状態ではなかったのである。私達は、その痛ましい姿をテレビのスポーツニュースでみることが出来た。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二試合には、兵庫の県立高校の川西緑台高校が初登場した。驚いたことに、エースの宮田投手は、肩の故障のためやっと2月から投球練習を始めたという。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三試合には、日田林工高校が登場したが、エースの江島投手は中指の故障をおしての登板であったらしい。なんと投手の故障が多いことか。また、なぜこんなことになってしまうのだろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「スポーツと訓練」(1990年5月14日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スポーツのための訓練についてのメモ。訓練には次の2つの側面がなければならない。ひとつは、無意識的にでも体が動くようにするためと、その訓練を最も効率的に行うためや試合をどの様に戦うかを臨機応変に決定するために、個々の選手が常に討論と考察が出来るようにするための訓練である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本では、2つ目の観点が全く欠け落ちているためか、あるいはこの部分が選手には全く任されていないためにか、この点についての訓練が全くなされていないのが現状である。これは、何もスポーツ選手のみの問題ではなく、日本という国に住む人間に欠落した部分である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
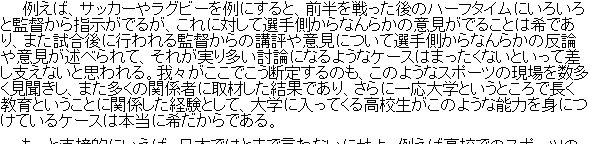
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
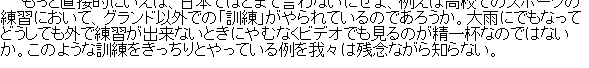
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
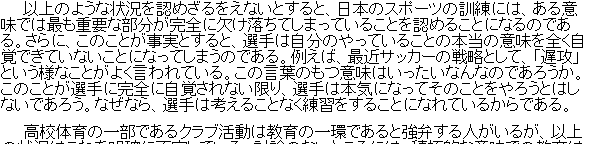
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
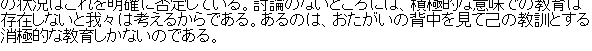
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上のような状況下でのゲームでは、その勝敗の行方は、相手のミスをいかに誘発するか、ミスを誘発するようにいかにスピーディにゲームを進めるか、ミスを避けるためいかにスタミナを強化するかなどにかかっている。アイディアの勝負ではないのである。そのためスピードのある選手を集め、極限までスタミナの強化を図るという成長途上の選手にとって危険な訓練を余儀なくされるのである。これは野球、サッカー、ラグビーをはじめとするほとんどのスポーツ競技の練習で行われていることである。その行き着く先は明白である。絶え間ない怪我による選手生命の短命化、指導者と選手の間の上下関係の強化、選手間における上下関係の強化を招くと共に、相手のミスを極端に喜ぶ選手心理、ファン心理を育てている。相手のすばらしいプレーにたいして拍手をする余裕などどこを捜してもでてこない。これが「スポーツマンシップにのっとり‐‐‐‐‐」とよく開会式で宣誓される高校教育の一環であるスポーツの姿だろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上で、今の日本でのスポーツの勝敗は、必然的にアイディアではなく技術の勝負になることを述べた。アイディアのほとんど全ては外国から来るのである。分野こそ違え、技術開発で休暇さえまともにとる雰囲気のない日本の技術者集団と、日本のスポーツマン諸君の雰囲気のなんとよく似ていることかと驚かされる。ただ選手の状況の方がもっと悪化している。つまり、技術の習得、開発に費やす時間に全く恵まれないばかりか、その基礎になる勉強に精を出す時間が全くない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先にも述べたごとく、ぎっしり詰まったスケジュールがこれを許さないのである。高校生や中学生ですら放課後から夜までの練習が一般化し、休日は全て大会か練習試合に明け暮れていてはなんの勉強もできない。成績が悪くなるのは当然である。今の制度では成績が芳しくなければ進むべき学校も制限され、選手自身が進歩する道は閉ざされるのである。考えてみればなんと閉塞的な状況であろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
きっちりした常識を持ち、物事をきちんと考える選手も数は少ないがいる。そうゆう選手が活躍できるのは、個人競技に限られていると言っていい。団体競技の場合には、そうゆう選手が1人や2人いてもうまくいかないのである。そんなに考えなくても技術の習得は出来るという人がいるかも知れない。確かにある程度のことは出来るであろう。しかし、そのことのもつ意味を自分が100%納得していない限り、とことんそのことに打ち込めないのが人間のやることであろう。また中途半端に習得した技術など外国にでれば全く役に立たないのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上述べたごとく、スポーツとそのために必須な訓練の問題は、教育を含む日本の文化の問題と言って差し支えないのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「草野球について考える」(1990年5月12日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「自由が丘キラーズ」について
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勝負を抜きにしてはおもしろくないと思われがちな野球であるが,必ずしもそうではないことを証明したい.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名古屋市の東部丘陵地帯自由が丘を拠点にして,「自由が丘キラーズ」という早朝野球を主とする草野球チームが197?年に発足した.このチームのメンバーは、おもに地元商店街の野球好きなだんな連中を集めたもので,今まで野球をやったこともないが,一度やってみたいと願望していたお世辞にも上手とはいえない人から,セミプロ級の人まで,幅広い人材が集まっていた.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
こういう草野球チームは全国津々浦々にあり,定期的にゲームを行なうために地域の連盟に所属し,指定されたグランドでリーグ戦を戦うのが普通である.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
しかし,このチームはどの草野球チームもが歩いて行くような道を行かなかった.3〜4年間にわたる粘り強い話合いの中からいっけんあたりまえと思われるが,実行が極めて困難である次のような方針が確認されることとなった.1)投げ,打ち,走り,そして守るという野球の基本的プレーを通じて,体を動かすことを楽しみとし,それによる健康の増進を最大の目的とする.2)野球を愛し,参加を希望する人については,30才以上で,行なうゲーム数の2分の1以上に出場して,決められた運営規則を厳守する限りにおいて,できる限り排除せず,できる限り公平な出場機会を与える.3)勝負を優先しない.4)この方針に基づいてクラブを運営するために,投票によって選ばれた運営委員長と6名の運営委員からなる運営委員会を月一度開催する.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上の確認事項を守るためには,チーム編成とルール面において普通では極めて稀な様々な変更が必要であった.1)勝負にこだわりがちなリーグへの加盟はせず,「自由が丘キラーズ」内での紅白試合を主とする.2)このことを可能にするために40名ほどのチーム編成とし,これを「白」「グレー」の2チームに分ける.3)多くの人が参加できるようにシーズンは1月から12月までとし,年4回紅白チームの編成替えをする.4)ゲームにおいては,全ての参加者が打席に立てるようにする.例えば,15名の参加があれば打席順は1から15番まで作る.5)守備の交代は自由とし,一度ベンチに入った選手も再び守備機会を持てるようにする.また,ピッチャーは最大3回で交代するものとし,試合時間は自由に変えられるものとする.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この様なやり方は,外からみれば,「なんだ紅白試合か」と言われ,打席順の意味も考えようがないし,ちっとも打順が回ってこないと不満に思えるかもしれない.しかし,やってみるとこれが実におもしろいのである.知りつくした相手とのかけひきは興味がつきない.体力的にあまり無理をする必要がなく,勝負のみにかける気持ちを,基本プレーの一つ一つにかけ,それをお互いに評価しようとするからである.その結果,表彰制度も通常のもの以外に様々なものが考えられることは想像に難くないであろう.会の運営に必要なクラブ費も,クラブ員が多いこともあり,今だに月2千円である. このようなユニークな「自由が丘キラーズ」のメンバーは様々な職業を持った人たちで構成され,名古屋市外からの参加者も多く,大きな広がりをみせている.毎週日曜日,夏は朝5時,冬はまだ暗い6時にはグランドに集い,それぞれゲーム前後に和気あいあいとおしゃべりを楽しんでいる.発足以来??年,年平均50試合以上の紅白ゲームを行ない,全体的なレベルの向上と維持のため,年に10〜15試合ほどの対外試合をすることで,かなりのチーム力を持っている.自由が丘でフトン店を営む河合氏は,本年53才でありながら,毎年ほぼ全試合出場である.彼もお世辞にも上手とは言えないが,依然としてこのチームに所属しているのは,ただ野球が好きで,体を動かすことの楽しさを知り,年数本のスカっとしたヒットを期待しているだけではないのである.多分それは,たとえ下手であっても,上手な人と同様にチームに貢献することのできるようにチームが編成されているからであろう.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
発足以来20年,その時々に応じてルールを自在に変えながらも,依然として活発な活動を続けるこのチームを支えているのは,話合いを積み重ねる運営方法と,スポーツをみんなで楽しみたいとする強い願望である.そのことを実現するため,今まで述べてきたこと以外に,クラブ員は等しくグランドの確保に全力をあげてきた.知人,友人を頼ってグランドを借り受け,また抽選のため名古屋市内の公共の土木事務所に早朝から並ぶことも度々であった.しかし,このチームにとって最も重要な展開は,平松,中西(私の兄)ら多くの方々の努力によって,有力企業がチームを理解し,そのグランドの利用を日曜,祝日の早朝に限って許可してくれたことであった.クラブ員はその行為に応えるべく,また,グランドの利用者として当然のごとくして精一杯の整備を行なっている.この良好の関係が続く限り,「自由が丘キラーズ」は安泰であろう.極言すれば,このように確実に使用できるグランドの存在こそが,今まで述べてきた様々な試みを可能にしているのである.この意味からすれば,我々が利用し得る公共の野球場はまったく不足しているのが実状である.今の日本では野球はまだ恵まれている.はたしてサッカーや別のスポーツをする場がじゅうぶんあるのか,という疑問はまた別の章で扱いたい.とにかく誤解を恐れずに言えば,近代スポーツの中に秘められている人間疎外をできる限り排除するためには,スポーツをする人たちがその実体をよく理解するだけでなく,スポーツをする場ー設備ーが社会的に保証される必要があるのである.逆に考えれば,スポーツの良き指導者と危険のない優れたスポーツ施設の不足は,確実に増えつつある余暇にスポーツを楽しもうとする市民を,ますます精神的苦痛の状態に追い込み,労働時間の短縮とは裏腹に有効な休暇の利用は不可能となっていくのである.戦後,国民の健康と体力増進を目的とした国民体育大会も全国を一巡し,現在二周目に入っている.これにともない,多くの立派な施設が建設されてきたことは事実である.しかし,この様な施設ですら十分な維持管理が行なわれておらず,ましてや一般市民が気軽に利用できる屋外施設の状況は悲惨である.市民レベルのスポーツに対する行政のなすべきことは,このことからだけでも明かであろう.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(付記:私が大阪に移った平成2年以来残念ながらそれほど多くのゲームに参加したわけでもないが、事情はほとんど変わっていない。ただ、若い人で野球を自分で楽しむ人が極端に減ってきたようである。私にとって大切な自由が丘キラーズへ、昨年は遂に1試合も出場できなかったのは全く残念であり、メンバーに申し訳なく思っている。今年もまだ出場できていないが、今年の夏には是非数試合は出たいと念願しているー平成10年(1998年)6月4日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|