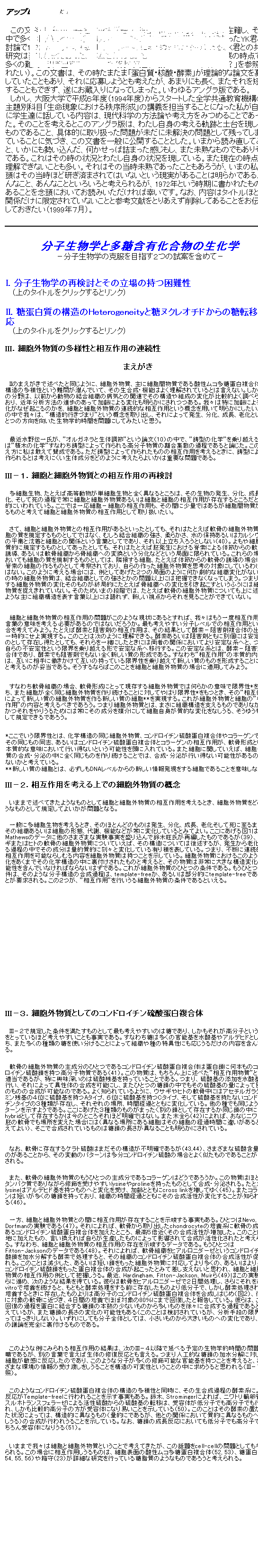
| ||||

|
||||
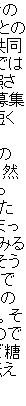
|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||
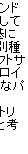
|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||

|
||||
| III−4.”相互作用”の限界と”構造的行きづまり” | ||||
| それでは相互作用は際限なく続くものと考えてよいであろうか。しかし細胞の分裂から次の分裂、または環境による分裂停止、さらに大きな事としては細胞、組織あるいは個体の死が存在するからには、この”相互作用”の中に何らかのかたちで限界を持たなければならないことは明らかであり、それが規定されない限り多くの矛盾を含んでくる。 | ||||
| ここで・−2で述べた細胞外物質の概念規定を思い出していただきたい。そこで我々は”非常に大きな構造変化の可能性を含んでいなければならない”と規定している。つまり、構造は生合成の過程においても、後からの修飾においても容易に変化しうるが、しかしその変化は”有限”である。たとえば、最も考えやすいコンドロイチン硫酸蛋白複合体を考えてみよう。この分子の糖鎖は蛋白に結合しているが、その siteには限りがあり(セリンの数には限りがある)、また長さも蛋白との関係において規定される。また糖鎖中の硫酸基の数は、特殊な場合を除きその糖鎖の長さと官能基の数以上にはなり得ないことは明らかであろう。 | ||||
| この観点で図1を見直すとひとつ重要な点が存在する。それはコンドロイチンタイプといわれる硫酸基のないN-アセチルガラクトサミン残基の量が胎児期の中期から終わりにかけて徐々に減少して行くことである。その時の細胞がアセチルガラクトサミンの4位と6位に硫酸基を導入する2つの酵素しか持たないならば、この相互作用は胎児期の末期に構造的な変化の限界、つまり”構造的行きづまり”を実現してしまう。軟骨細胞は、さらにこの限界を乗り越える形であたらなケラト硫酸の合成を開始する。この分子もコンドロイチン硫酸蛋白複合体同様にその微細な変化を観察すれば、たとえば硫酸含量の少ないものから多いものへと変化していると考えても不思議ではない。しかし、40才位のところからほとんで変動がないことは、軟骨組織として完全に限界に到達し、それ以上の新たな情報を引き出せないことを示している。 | ||||
| これまでの議論の中で重要なことは次のことである。すなわち、我々が扱おうとしてきた”相互作用”は、その構造上の裏付けとして、コンドロイチン硫酸蛋白複合体の場合、糖鎖の数としては少ないものから多いもの、すなわち分子としては小さいものから大きいものへ(Hardinghamら)、また硫酸含量としては少ないものから多いものへ(図1)、そして糖鎖の長さとしては短いものから長いものへ(木全ら)と変化していることである。このことは”量”ということで一般化したとき、小から大への一方向の変化しかないことを示しており、少し飛躍するが、たとえば個体は小さいものから大きいものへとしか変化しないことと一致して興味深い。 | ||||
| III−5.”構造的行きづまり”とその生物学的意味 | ||||
| いままで扱ってきた軟骨のデータ(図1)でこの両者の関連をみてみたい。まず、胎児期の中期から終わりにかけてCタイプとコンドロイチンタイプの合成が減少し、これがAタイプの増加と一致する。全てのアセチルガラクトサミンの4位と6位がふさがれて硫酸の入れる位置が無くなるとという限界に近づくと、それを乗り越える形でケラト硫酸の合成が行われる。この変化が定常状態になったとき、その組織としての限界に到達していると考えられるが、しかしこの場合新しい細胞外物質を作り出す情報を遺伝子の中から引き出せないことを示している。すなわち、アセチルガラクトサミン残基が硫酸残基によって修飾されたものを作る過程が原基形成であり、新しくケラト硫酸合成による”相互作用”の克服過程がAdultの軟骨組織への”成長”過程である。しかしながらケラト硫酸の構造が変化の可能性を失って固定化したものになり、しかもこれに情報の有限性が関係したとき、その組織は次第に”老化”して他の細胞にとって代わられるか、組織が崩壊するかのどちらかとなってしまう。だか、なぜ”老化”するかはわからないが*、いまのところ合成抑制による細胞活性の低下としか言い得ない。 | ||||